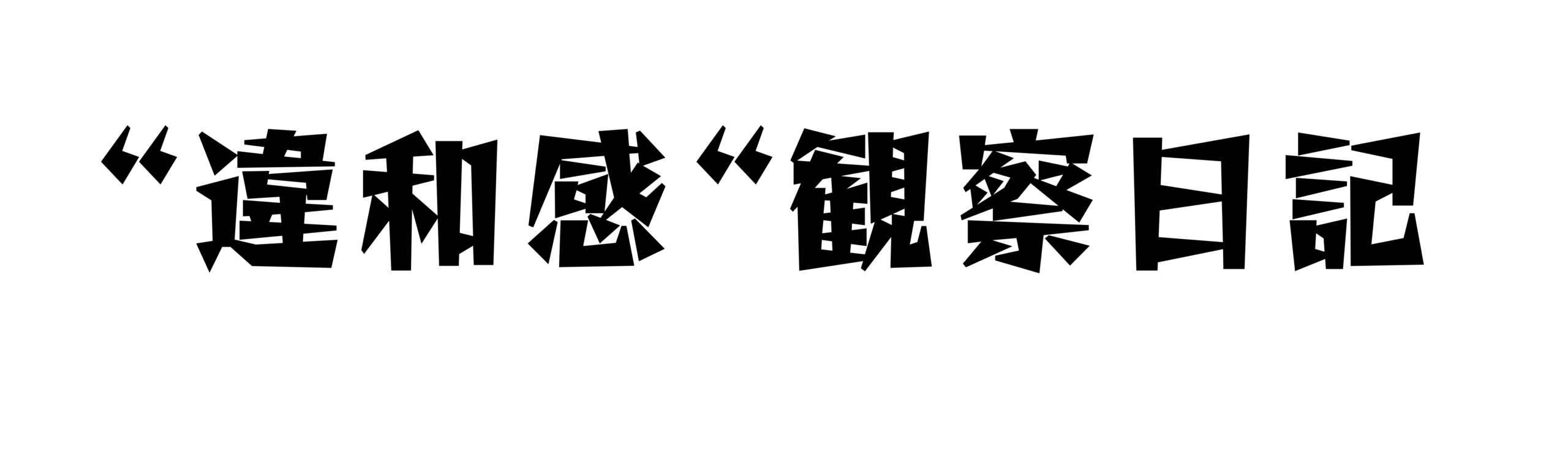こんにちは、山本(@ay011_8)です。
ブログとかnoteとか、書こうと思っても「何書けばいいんやろ…」って手が止まるとき、ありませんか?
で、そのまま放置してると、
「自分は発信向いてないかもな…」って、無意識のうちに勝手にレッテル貼り始めるんですよね。
地味に怖いのがこのパターン。
でもたぶん、才能とかじゃなくて。
ただ「問いの立て方」がちょっとズレてるだけ、ってことがほとんどです。
なので、こんな問いを、自分に投げかけてみてほしいです。
- 最近、なんかモヤっとしたことってあったっけ?
- 誰かとの会話で、不意に「うわ、そうかも」ってなった瞬間は?
- 昔はスルーしてたけど、今なら拾えそうな感情って?
こういうのって、誰かの役に立つかどうかは正直あとでいいと思っています。
むしろ、自分がちゃんと“引っかかったこと”のほうが、他人にもちゃんと届く気がしてて。
だから、「書けないな」ってなったときは、“うまいネタ”を探すんじゃなくて、“ちゃんとモヤついた自分”を探してみる。
それが、発信を「がんばってやるもの」じゃなくて、「ただの生活の延長線上」に変えてくれます。
息を吸って吐くみたいに、ふとした瞬間に、言葉がこぼれるようになる一歩です。
じゃあ、どうやって「ネタ」って拾えばいいの?
正直、“探す”って感覚じゃなくて、“気づく”って感覚に近いです。
ネタって、すごく日常に溶け込んでるんですよね。
目の前で起きてることよりも、「それをどう受け取ったか」のほうが、発信のタネになる。
たとえば──
- スマホでなんとなくスルーしようとした広告に、なぜか引っかかった。
- スーパーで隣にいた人のひと言が、妙に頭から離れない。
- 朝起きた瞬間の「だるいな」に、何かが詰まってた気がする。
そういう“違和感のかけら”を、そのままにしないこと。
それだけで、ネタは勝手に増えていきます。
ネタの掘り下げもやることは一つだけ
「これってなんで気になったんだろう?」って、自分に問いを足してみること。
- あの広告の言い回し、なぜイラっとしたんだろう?
- 隣の人のひと言、自分のどんな経験と重なったんだろう?
- その“だるさ”って、どこから来てたんだろう?
って感じで、“自分の反応”を観察してみる。
誰かの役に立つかどうかは、一旦置いておいていいです。
そのうえで、「これ、自分にしか書けない気がする」と思えたら、もう勝ちです。
だからネタ探しって、本当は“情報収集”じゃなくて“自分観察”なんですよね。
人を見つめるより、自分を見つめるほうがネタになる。
で、書いてみて初めて、「あ、自分ってこういうとこ気にしてたんだな」って気づくこともありますし。
そういう意味で、発信って“自己理解の副産物”だったりするんじゃないかなと思っています。
とはいえ、「気づくって言われてもピンと来ない…」って人もいるかもしれません。
そんなときは、“今日1日を逆再生してみる”のがおすすめです。
寝る前とかに、軽くでいいので振り返ってみてほしいんです。
- 朝、なににムッとした?
- 昼、どんな違和感を飲み込んだ?
- 夜、誰の言葉がちょっと引っかかった?
これ、全部ネタになります。
むしろ「これって発信ネタになるかな?」って思った瞬間に、ネタっぽくなくなっちゃうので、
“引っかかったままの感情”をそのまま置いてみるくらいがちょうどいい。
もう一歩だけ進めると、
「ひっかかりメモ」をスマホのメモ帳に一言だけ残しておくのもいいです。
たとえば──
- 「何が分からないか分からないよ」って上司からの言葉に、なぜかイラッとした
- 電車で咳してる人にちょっと距離を取ってしまった自分にモヤった
- 昔の自分なら言えなかったひと言が、今日は自然に出てた
1日1個だけでも十分です。
あとから見返すと、「あ、この時、何か大事な感情を握ってたな」ってわかるようになります。
そうやって自分の“かすかな揺れ”を拾っていくだけで、もう発信ネタに困らなくなります。
というか、“ネタがないっていう発想がズレてた”って気づいてきます。
発信って、ネタ探しじゃない。
自分の中で、まだ言葉になってないものに、言葉をあげること。
その行為そのものが、自分をちょっとだけ知るきっかけになるのかもしれません。