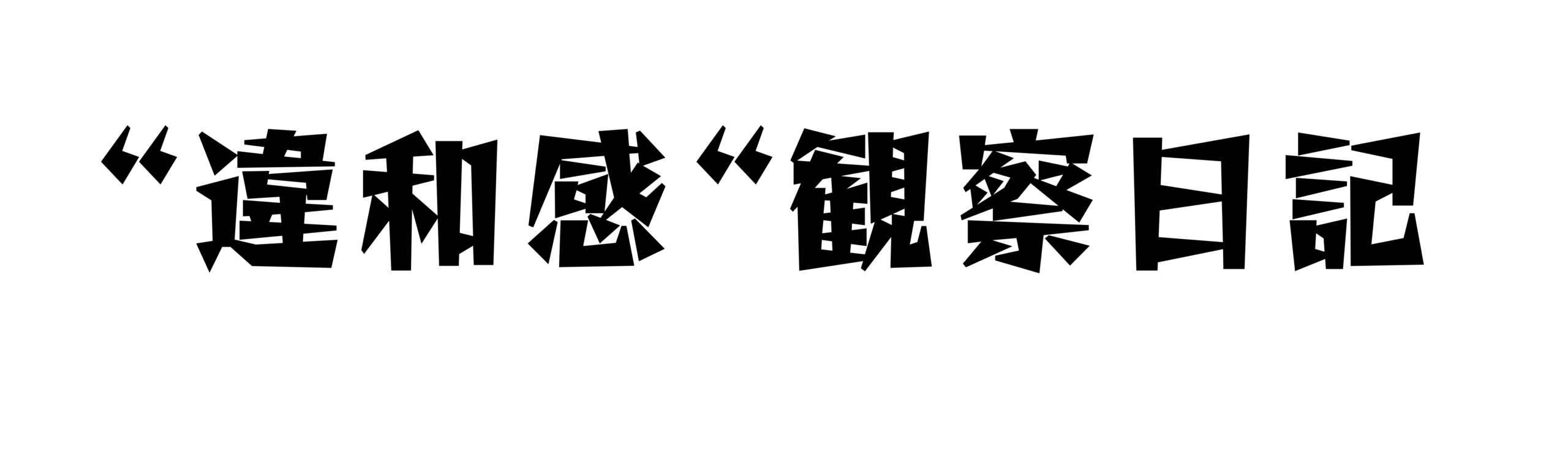こんにちは、山本(@ay011_8)です。
いきなりですが、自分の人間関係が崩れていくときの「パターン」って、把握できていますか?
どこに行っても、なるべくうまくやろうとしているのに、
気づけば空回りして、最後には自分から関係を遮断してしまう。
僕はずっと、その繰り返しでした。
結論から言うと、
僕が人間関係を壊してしまう最大の要因は——
分析への過度な依存です。
相手を“先読み”して、関係を終わらせてしまう
たとえば僕は、愚痴を聞く立場になることが多いんですが、それ自体に抵抗はありません。
話してスッキリしてくれるなら、それでいいと思って聞いています。
でも、ふとした瞬間にこう思ってしまうんです。
「なんでこんなに愚痴ばっかり? 俺の時間、奪われてないか?」
もちろん、相手にはそんなつもりはない。
けれど僕は、“奪われている”という解釈を、勝手にしてしまう。
そして、気づかないうちに結論づけている。
「この人と関わってたら、自分がダメになる」
完全な被害妄想ですが、
でもその瞬間にはもう、関係を切る準備に入ってしまっているんです。
なぜ、そんな思考パターンができあがったのか
思い返せば、その原型は――小学校四年生の「転校」でした。
当時の僕は、日常に何の不満もありませんでした。
毎日決まった時間に登校し、放課後は友達と遊び、帰り道に駄菓子屋に寄って。
何気ない日々が、ただただ、心地よかった。
そんなある朝、母に言われたんです。
「大事な話があるから、今日は早く帰ってきて」
なんだろう?と思いながら、授業中もどこか落ち着かずに一日を過ごし、
急いで家に帰ると、母の口から出たのは、
「転校するかもしれない」
一瞬、意味がわかりませんでした。
なんで??どこに?誰が決めたん?
質問が頭の中をぐるぐると回る。理由は、住んでいたアパートの取り壊しと、地域の治安の悪さだと説明されました。
でも、そんな理由じゃ僕の気持ちは全然整理できなかったです。
「転校したくない。友達とも離れたくない。今のままがいい」
必死に伝えた言葉に、母はこう返しました。
「もう決まったから。ここにいるより早めに転校した方がいい」
その瞬間、なんとも言えない冷たさを感じました。
話したとしても、決まったことは変わらないんだなと。
いじめと「会話が成立しない世界」
転校先では最初、不安とは裏腹にすぐにクラスのみんなと打ち解けることができました。
「あれ?意外と大丈夫かも」と、ほっとしていた矢先のことです。
けど、翌年のクラス替えで一気に空気が変わります。
翌年のクラス替えで、空気が一変します。
ある日、ほとんど話したこともない同級生が、僕の前でこう言いました。
「あいつ、無視しようぜ」
何やそれ?意味わからんわ。
なんで?話したこともなければ、何もされてないし。
当然、そんな指図を受けなかったんですが、気づけば自分も加害者になっていて、そのうち、今度は自分が無視される側になってい舞ました。
これまで普通に話していたやつが、急に目を逸らす。
名前を呼ばれなくなる。笑い声が聞こえるのに、自分だけその輪に入れない。
何が起きているのか、本当にわからなかったです。
どうしても耐えられなくなって、母に泣きながら言いました。
「学校に行きたくない。もう無理だ。行きたくない」
今にも崩れそうな自分の声を絞り出したその瞬間、母から返ってきたのは、たったひと言。
「堂々としてなさい。行かないと、余計に悪化する」
たしかに正論だとは思うんですよ。
でも、その時の僕にとっては、「助けて」という声をはね返されたように感じました。
話しても、伝わらない。言っても、無駄。
「この人には、もう何を言っても通じないんだ」
そんな感覚が、あの時、心の奥に静かに沈んでいった気がします。
分析が「武器」であり「呪い」になった
あの転校、そしていじめの経験を境に、
僕の中の“世界の前提”が、音もなく書き換えられていきました。
「この人に何を言っても無駄だ」
「どうせ、本音は受け止めてもらえない」
そんな感覚が、日常のあちこちに滲んでいて、気づけばそれが「当たり前」になっていました。
それ以来、人との関係で違和感を覚えるたびに、僕は“分析モード”に入るようになりました。
ちょっとした言葉のトーン、目線のズレ、反応の間。
そのたびに、頭の中では静かにシナリオが始まるんですね。
「あ、この人たぶん俺のこと軽く見てるな」
「今は優しくても、そのうち手のひら返すやつかもしれない」
「深入りしないでおこう。期待しないほうが楽だから」
ほんとはただの違和感なのに、それを“確信”に変えていく作業が、習慣のようになっていきました。
そんなふうに、自分を守るために先回りして人との距離を取って、気づけば関係が深まる前に、自分から壊していました。
ほんとは繋がりたかったのに、怖さをごまかすようにして、先に壊してしまう。
それが結果として何を生むかというと、やっぱり孤独なんですよね。
「やっぱり人って、信用できない」
「ほら、また一人になった」
そうやって、自分が作り上げたストーリーが正しかったことを、自分自身で証明し続けるループに入っていく。
気づいたときにはもう、“人と近づく”ってこと自体がめんどくさくなっている状態になっていました。
あとがき:パターンを知ると、選択肢が増える
僕の場合、
「この人に何を言っても無駄だな」
そう思った瞬間から、人間関係の終わりが始まります。
自分では静かにフェードアウトしてるつもりでも、実際はその時点で、もう心を閉ざしてる。
でも最近は、そんな瞬間にこそ問い直すようにしています。
「それって、本当に“いま目の前のこの人”にも当てはまる?」
「それ、ただの“過去の再演”じゃない?」
僕にとっての「分析」は、過去の地雷を避けるための知恵でもあるし、
目の前に咲いている花まで踏みつけてしまう呪いでもある。
どちらにもなり得るからこそ、
自分の“パターン”を知っておくことには、意味がある。
それがわかるだけで、選べる未来が、ほんの少しだけ増える気がしています。